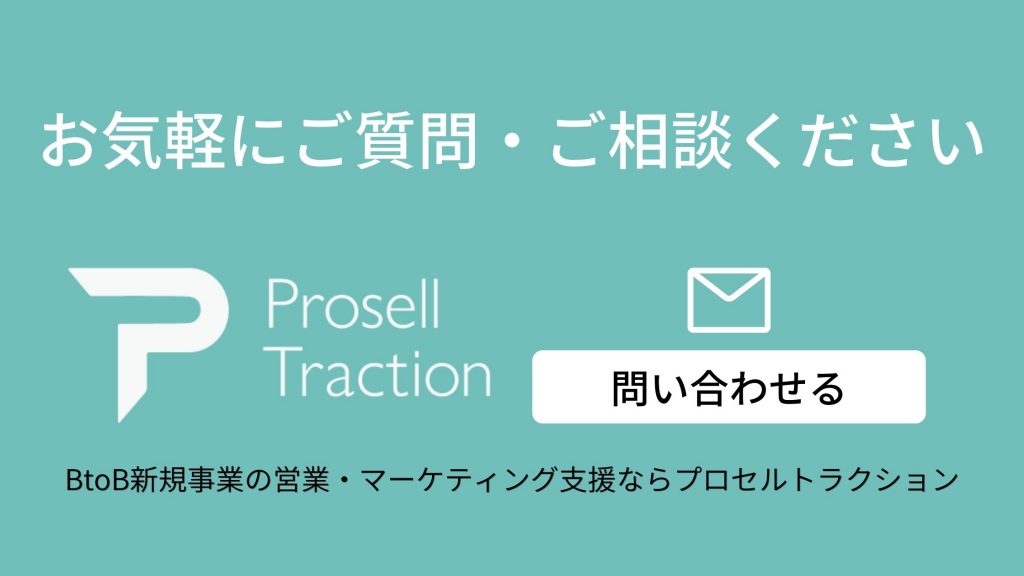近年、技術革新のスピードが増す中で、どのような画期的な商品やサービスにも、やがて市場が飽和し、成熟期・衰退期が訪れるのはやむを得ないことです。
製品ライフサイクルが短期化する傾向にある昨今、企業が中長期的な成長を続けるためには次なる収益の柱となる新規事業を継続的に創出し続けることが必須です。実際、安定した経営基盤を持つ大企業でも市場変化に対応するために新規事業開発へ積極的に取り組むケースが増えています。
しかし、資本が豊富な大企業ほど、新規事業の創出に苦しむケースも目立ちます。企業カルチャーやリーダーの資質によっても、新規事業の重要性は理解されつつも、成功する事業を生み出し、伸ばしていく作業は容易ではありません。
本記事では、大企業が新規事業を成功させるための具体的プロセスについて、アイデアの発掘から事業化までのステップを解説します。
大企業が新規事業を成功させるプロセス
新規事業立ち上げには体系立てた思考と実行のプロセスが求められます。アイデアの創出から事業化までの基本的なプロセスを説明します。
事業ドメインの設定とアイデアの発掘
まず取り組むべきは、どの領域で事業を展開するか(事業ドメイン)を定めることです。自社の強みや社会のニーズを踏まえ、参入すべき市場や解決すべき課題の領域を明確化し、その領域に関連する顧客の課題やニーズを徹底的に洗い出し、新規事業のアイデアを創出します。
顧客が求めるものは製品そのものより「自分の抱える課題の解決」であることを捉え、現状では満たされていないニーズを探り当てることが重要です。この段階では、業界動向の調査や競合他社のサービス分析を行い、潜在的な需要や未解決の課題を多角的に調査します。
ビジョンの明文化と共有
アイデアの方向性が定まったら、新規事業のビジョン(将来的に実現したい姿や社会への提供価値)を明確化します。ビジョンは単なるスローガンではなく、事業を進める上での羅針盤であり、チームメンバーの拠り所となるものです。
メンバー全員がそのビジョンを理解し共有できるように言語化し、繰り返し浸透を図ることが大切です。ビジョンが明確で共有されていれば、プロジェクトチームが一丸となって困難を乗り越え、事業を推進する原動力となります。反対にビジョンが曖昧だと方向性がブレやすく、意思決定も迷走しがちです。
市場調査と事業性の検証
次に、設定した事業ドメインとアイデアに関する市場性や事業性の調査・分析を行います。
具体的には、3C分析を行い
- ターゲット市場規模
- 成長性
- 競合の状況
などを調べ、どれほどの需要が見込めるかを定量的に把握します。
同時に、ターゲットとする顧客層のニーズや購買要因を深掘りし、自社の提供価値が十分に魅力を持つか検証します。市場の将来性や参入障壁、競合優位性などを評価し、ビジネスモデルを具体化するプロセスがこの段階で必要です。
こうした調査結果をまとめた結果、事業計画書がまとまっていきますが、社内の承認を得るためにプランのスケールがダウンサイジングされるケースが少なくありません。たしかに資金調達のために、検討内容を現実的で実行可能なレベルに落とし込むことも重要です。
特に大企業の新規事業では社内承認に時間を要する傾向があるため、当初描いていた志が折り曲げられてしまう場面もあるようです。ここで当初のビジョンに立ち返ることが重要となります。
アセット・リソースの確保と開発準備
事業計画の詳細を固めつつ、大枠の承認後には新たな製品やサービスを開発するためのアセットやリソースの確保に動きます。新規事業には「ヒト・モノ・カネ・情報」の経営資源がバランスよく必要です。
大企業の強みは、多様な特性やスキルをもった人材を有し、開発やマーケティングなどにかかる一定程度の資金的な余裕があることです。反面、新規事業に取り組んだ経験のある人材が不足し、情報不足に陥るケースもあります。
自社内のアセットが十分でないと判断されるときは、いわゆるオープンイノベーションで、外部の力を活用することも考えるのがよいでしょう。社外の専門人材や技術を取り入れることは、新規事業の推進に有効な場合が多く見られます。
自社にないノウハウは外部のパートナー企業・専門家との連携によって補完し、効率的に開発を進めましょう。
ガントチャート作成と実行フェーズのPDCA
いよいよ事業化に向けた具体的なロードマップ(行動計画)を策定します。さらに期限やステップへ落とし込んでガントチャートを作成するのも有効です。
プロジェクトの各フェーズで「いつ・誰が・何をするか」を明確にし、スケジュールとマイルストーンを設定しましょう。
ただし新規事業が、初期に想定した通りに進行することはまずないでしょう。想定していなかったトラブルや環境変化によってスタックする場面に備えて、計画には余裕を持たせ、変化に柔軟に対応できるようにします。
ガントチャートは、実行フェーズに移行してからも常にアップデートとメンテナスを繰り返すこととなるでしょう。計画した施策が期待通りの成果を上げているか都度検証(モニタリング)し、必要に応じて軌道修正することが欠かせません トラブル時も、検証結果にもとづき素早く学習・改善を回すことが成功の鍵となります 。これをリーンスタートアップといい、最低限のコストで小さく事業を開始し、顧客の反応を見ながら製品やサービスを迅速に改良していく手法です。このようにスピード感を持ってPDCAを回し、市場のニーズに合致する形へと事業を磨き上げていくことが成功のポイントとなります。

大企業が陥りやすい課題と対策
新規事業プロセスを追いかける中で特に大企業ならではの課題も存在します。ここでは新規事業立ち上げ時に大企業が陥りがちな問題点とその対策を整理します。
意思決定の遅さ
大企業では部署横断の調整や多層的な稟議承認が必要なため、ベンチャーに比べて意思決定に時間がかかりがちです。
当初は優れたアイデアで他社より先行していても承認を待つ間に市場機会を逃す恐れがあります。プロジェクトチームの発足から調査にかかる予算の獲得までに年単位の時間がかかるようなケースもあります。
本来の大企業がもつリソースを全く活かせず、小規模ながらもフットワークの軽い組織の後塵を拝することがあるのは、このスピードの遅さが最大の原因です。
この対策として、小規模で独立した新規事業専任部門を設置し、既存組織からある程度自立した形でプロジェクトを進めることが有効です 。独立部門にすることで他部門の承認プロセスに左右されにくく、スピード感のある意思決定と行動が可能になります。
社内ベンチャー制度などを活用して、新規事業チームの独立性を認め、社内カンパニーのような運営を行う企業もあります。
既存事業や過去の成功体験にとらわれる
大企業には、長年自社のビジネスを支えてきた既存事業があるものです。そして、その成功体験の存在があるために、どうしても従来の主力事業の延長線上で物事を考えがちです。
結果として革新的なアイデアがスポイルされたり、新規事業に十分な経営資源を割けなかったりすることがあります。
そこで経営トップが新規事業にコミットし支援する姿勢を示し、評価指標を既存事業と切り離すような仕組みも大切です。また、他社での新規事業成功例を研究したり、社外の知見を取り入れることで視野を広げ、既存の枠にとらわれない発想を促す工夫も有効でしょう。
経験豊富な人材・ノウハウの不足
新規事業開発の経験を持つ人材が社内にいない場合、手探りで進める中で試行錯誤が増え、効率が悪くなります。特に最新のデジタル技術や新市場の知識が不足していると、適切な戦略立案や意思決定が困難です。
小規模な組織は、はじめから自社のリソースが不足していることを理解しているため、外部人材を迎え入れることに抵抗がありません。しかし、大企業の中には、自社に適切な人材がいないにもかかわらず、相対的に適性のありそうな人物をアサインしてしまうことがあります。
新規事業立ち上げの実績を持つコンサルタントの言うことがすべて正しいわけではありません。しかし客観的な目線で自社のビジネスプランやチーム体制を評価し、指導してもらう方法はひとつの対策として有効です。社外の知見を柔軟に活用することで、自社に不足する経験値を補い、プロジェクトの成功確度を飛躍的に高めることができます。
営業戦略の重要性とその課題
優れたプロダクトやサービスができあがったとしても、それが自社の評価だけでは意味がありません。市場に受け入れられ収益を上げるためには、まずPMF(プロダクト・マーケット・フィット)が重要であり、その見極めには的確な初期の営業戦略の立案と実行が不可欠です。
これまで多くの新規事業が失敗した要因として、マーケティング・営業戦略の不備が挙げられきました。適切な市場でマーケティング活動を行い、必要とする顧客が多くいる状態を作り出せなければ事業としては成り立たないためです。
新規事業の立ち上げ時には、「顧客は誰か」「どのようにその顧客にリーチし提供価値を伝えるか」というGo-To-Market戦略を早い段階で明確にする必要があります。
しかし現実には、新規事業の初期段階では営業面で次のような課題に直面しがちです。
営業リソースの不足
新規事業のプロジェクトは人員や予算が限られているのが普通です。特に力のある営業担当は、既存事業の営業活動に忙しく、専任で新規事業を担当できることは多くないでしょう。
この傾向は、大企業で優秀な人材ほど顕著な傾向にあると言われています。新規事業は最低限のチーム体制でスタートするケースも少なくありません。その結果、営業活動が後手に回り、市場での認知獲得が遅れる恐れがあります。
したがってマーケティングから営業のフェーズになった段階で、思い切った体制の強化が求められます。
営業スキル・ノウハウの不足
新規事業の営業では、既存のビジネスとは異なる営業スタイルやスキルが求められることも多くあります。すでに確立された市場で営業の実績を積み重ねてきた経験は、新規事業にはまるで当てはまらない場合も少なくないのです。
加えて、限られた予算ゆえに若手や未経験のメンバーが営業を担わざるを得ず、育成に時間がかかるケースも多いようです。この場合、営業的なスキルが未熟で、適切な勝ち筋を見いだせないこともあるでしょう。見込み客の発掘から成約まで、営業プロセスを確立するスピード感が非常に重要ですが、未経験者には荷が重いと言わざるを得ません。
しかし、ここでエース格となる営業パーソンが、属人的なプロセスではなく、チームで再現可能な営業フローやトークスクリプトを用意することで、少人数でも、経験が少ないスタッフでも安定した成果創出が可能になります。実際、「人員を十分に集められない」「高スキルの営業がいない」という場合でも、適切なプロセスを整えれば限られたリソースで大きな成果を出すことができます。
顧客ニーズ・ターゲットの見極め不足
新規事業では特に最初の顧客ニーズ調査とターゲティングが重要です。よくある失敗として「顧客層を広げすぎてしまう」ケースがあります。誰にでも売れるようにターゲットを曖昧に広げたことで、製品開発のコンセプトや訴求メッセージも散漫になり、誰にも響かなくなるといった失敗例です。
むしろ、最もニーズの強い顧客像を明確に描き、その層に集中してアプローチする方が効率的です。そのためには、市場調査によって顧客の課題を正確に把握し、競合製品との差別化ポイントを明確にした上で、自社製品が応えられるニーズを絞り込む作業が重要です。
営業チャネル・手法の模索
新規事業では過去の販売実績がないため、どの営業チャネル(直販、代理店、オンラインなど)やマーケティング手法が効果的か手探りになることがあります。広告やプロモーションに多額の予算を投下する判断も難しく、消極的になってしまう場合もあります。
しかし、販促に躊躇があったり、適切でない宣伝手段を採用したりすれば認知は拡大せず、当然売上は上がりません。予算に制約がある中でも、低コストで効果検証できるデジタルマーケティングやスモールスタートのテスト販売を行い、最適な営業手法が何かを検証することが重要です。その検証を踏まえて資源配分を最適化し、本格展開時には効果の高いチャネルに集中投下する戦略を取るべきでしょう。
営業代行の活用とそのメリット
新規事業の営業課題に直面したとき、自社内だけで解決するのが難しい場合や、解決に時間・コストをかけられない場合は、営業活動を外部に委託(営業代行)することも有力な選択肢です。
営業代行サービスとは、専門の外部企業やプロフェッショナル人材に自社の営業業務を委ねる仕組みで、大企業の新規事業プロジェクトでも近年多く活用されています。
営業代行を活用する主なメリットは以下の通りです。
即戦力の営業を投入できる
経験豊富な営業のプロフェッショナルチームを即座に自社の戦力にできる点が最大の魅力です。
自社でゼロからメンバーを採用・育成する時間を節約でき、立ち上げ初期の貴重な時間を逃しません。新規事業の成功にはスピードが重要であるため、立ち上げ当初から高い営業力を発揮できるのは強みです。
営業ノウハウと戦略提案
営業代行会社は様々な業界・商材の営業支援実績を持っているため、効果的な営業プロセスや顧客開拓手法のノウハウが蓄積されています。単に人手を補うだけでなく、自社製品に合った営業戦略の設計から実行までワンストップで任せることも可能です。その結果、社内にノウハウを蓄積しつつ早期に成果を上げることが期待できます。
コストとスケーラビリティの管理
営業代行なら、自社で正社員を増やす場合と比べて柔軟な契約形態を選択でき、必要に応じて契約を拡大・縮小できます。
例えば、固定報酬型・成功報酬型など契約モデルを調整することで予算に合わせた運用が可能です。成果報酬型なら、成果が出なければ余計なコストが抑えられるため、新規事業における費用対効果の不安も軽減できます。
このように営業代行の活用は、新規事業の「営業がうまくいかない」という状況を打開する強力な手段になり得ます。実際、「ニーズはあるはずなのに売上が伸びない」「営業方法が定まらず手探りだ」といったケースで、外部の営業支援によって突破口を開いた事例も多数報告されています。自社内のリソースに限りがある場合は、専門サービスの力を借りることも前向きに検討すべきでしょう。
新規事業の営業代行ならプロセルトラクション
新規事業の営業代行なら実績が豊富なプロセルトラクションにご相談ください。
ともに勝ち筋を考え、PMFから、電話での追客や商談獲得、クロージングまで一貫した対応が可能です。新規事業のマーケティングとセールスに関するお悩みを解決に導きます。
大企業による新規事業の成功事例
最後に、実際に大企業が新規事業を立ち上げ成功させた具体的な事例を3つ紹介します。国内外を問わず多くの事例がありますが、その中から代表的なものを取り上げ、その事業が成功した要因とポイントを解説します。
事例1:ソニー・PlayStation
日本企業の新規事業成功例として、頻繁に紹介されるのが、ソニー株式会社による家庭用ゲーム機「PlayStation(プレイステーション)」事業の立ち上げです。
ソニーはオーディオや映像機器の大手メーカーでしたが、1990年代にゲーム業界へ新規参入しました。実は当初、任天堂のゲーム機向けCD-ROM拡張機器を共同開発する計画からスタートしましたが、この交渉が中途で決裂したことを契機に自社独自のゲーム機開発に乗り出しました。
家庭用ゲーム市場において、任天堂やセガの寡占化が進み、新規参入は極めて大きなリスクだと社内でも懸念されていましたが、当時としては画期的な3Dグラフィックスに特化した次世代ゲーム機は、ソニーの命運を大きく変えることとなります。
プレイステーションが成功した要因の中でも、特筆すべきは技術的優位性です。従来は、2Dが中心だったところに本格的な3Dグラフィックスを実現し、高品質なゲーム体験をユーザーに提供できたことが画期的でした。
また、ソニーは外部のゲーム開発会社に対して開発ツールや技術情報を積極的に提供し、サードパーティー戦略を採用してエコシステムの構築に力を注ぎました。これにより後発ながらも、開発のしやすさと高性能を背景に大手ゲームメーカーの参入が促され、人気ゲームタイトルが次々とプレイステーション向けに投入されるようになります。
当然の結果として、ゲーム機本体の販売も飛躍的に伸びる好循環が生まれました。新規事業において卓越したプロダクト力と戦略的パートナーシップの構築が重要だといえます。自社の強みである技術力を新分野に適用し、高性能プラットフォームを作り上げました。同時に、ゲーム制作者というパートナーへの訴求(開発環境整備や支援)を行うことでコンテンツ供給を確保し、市場シェアを獲得しました。
事例2:富士フイルム・ASTALIFT
2つ目の事例は、富士フイルム株式会社の事業多角化および転換です。社名のとおりかつて世界最大の写真フィルムメーカーとして知られていましたが、デジタルカメラやスマートフォンの普及によってフィルム需要が急激に縮小する危機に直面しました。競合であった米・コダック社が経営破綻したにも有名ですが、富士フイルムは自社のコア技術を活かした新規事業展開に踏み切ったのです。
写真フィルムの長年の研究開発で培われた技術には、化学・材料分野の高度なノウハウが数多く含まれていました。富士フイルムはその中でも、医療分野と化粧品分野に活路を見出します。例えば、X線画像用の高感度フィルム技術や画像処理技術を応用し、デジタルX線診断装置や内視鏡などの医療機器事業に参入しました 。
同様にこれまでフィルム材料に使用されていたコラーゲンや抗酸化技術に着目し、高機能化粧品ブランド「ASTALIFT(アスタリフト)」を立ち上げてスキンケア事業にも乗り出しました。写真フィルムで培ったナノレベルのコントロール技術や抗酸化ノウハウを肌のエイジングケアに応用し、高付加価値の商品を展開したのです。
成功要因は、自社の強みの転用とタイムリーな戦略転換にあると言えるでしょう。自社技術の強みを冷静に棚卸しして、他に応用できる分野を見極めたこと、そして需要のある成長市場(医療・美容)に対して、競合他社には真似できない独自技術で参入したことがポイントです。
大胆な組織改革と投資判断を行った経営トップのリーダーシップも見逃せません。これは大企業における既存事業の衰退に備えた戦略的ピボットの好例です。
事例3:ソフトバンク&ヤフー・PayPay
ソフトバンク株式会社とヤフー株式会社(現:Zホールディングス)は、合同でスマートフォン決済サービス「PayPay(ペイペイ)」の普及を目指しました。政府によってキャッシュレス決済推進の機運が高まる中、当時まだ日本のキャッシュレス決済比率が2割程度に留まる中で、アジア各国でのキャッシュレス事業展開戦略の一環として、日本国内でもキャッシュレス化を促進すべく新サービスの準備を進めたのがソフトバンクでした。
PayPayが成功した鍵は、スピード感ある立ち上げと大量ユーザー獲得戦略にあります。ソフトバンクは2018年、インドの大手決済プラットフォーム企業(Paytm社)の技術をベースにPayPayアプリを開発・リリースしました。他社の先進技術を活用することでサービスの迅速な立ち上げが可能になった事例であり、企画開始からわずか半年程度で本格サービスインを実現しています。
リリース後は、携帯電話キャリアとしてのソフトバンクおよびヤフーの顧客基盤を活かし、大規模なポイント還元キャンペーンを展開し、爆発的なユーザー数の増加に成功し、他社との競争を制しました。
開始から1年余りで数千万規模のユーザーを獲得し、現在では累計6,500万以上のユーザーが利用する国内最大級のキャッシュレス決済サービスに成長しています。
PayPayも外部リソースを大胆に活用し迅速なサービス開発を行ったといわれています。またポイント還元の施策が注目されがちですが、ユーザ獲得だけでなく、加盟店側への営業も積極的に行った点は見逃せません。
全国の中小店舗に対して決済手数料無料期間を設けたり、営業担当者や代理店を通じて端末導入を働きかけたり、地道な営業活動で利用可能店舗網を拡大しました。加えてテレビCMや各種プロモーションで認知を高め、サービス開始から短期間で日本全国に浸透させています。
まとめ
大企業が新規事業を立ち上げ成功させるためには、以上で述べたような綿密なプロセスの遂行と戦略的な対応が求められます。アイデア創出から市場調査、開発、そして営業に至るまで、一連のプロセスを着実に踏み、必要に応じて組織体制を工夫し外部の力も活用することが肝要です。特に、新規事業の営業面の出来如何が事業全体の成否を左右することを忘れてはなりません。優れた商品も、適切な顧客に届けなければ宝の持ち腐れです。営業戦略を練り上げ実行する段階で課題があれば、早めに手を打つことが肝心です。
本記事で紹介した成功事例に共通するのは、市場ニーズの深い理解と俊敏かつ柔軟な対応、そして周囲(社内外)のリソースを最大限に活かす姿勢です。新規事業は未知の連続ですが、適切な準備と体制づくりによってリスクを抑えながらチャレンジできます。大企業の強みである資金力や人材基盤もうまく活用しつつ、スタートアップ的なスピード感と顧客志向を持って臨むことが成功への近道と言えるでしょう。
自社で新規事業の立ち上げに取り組む中で、「営業戦略の立案や実行に不安がある」「限られた人員で効率的に市場開拓したい」と感じられましたら、ぜひ営業代行サービスの活用を検討してみてください。専門サービスを利用すれば、営業戦略の策定から実務までプロに任せることができ、貴社はコア業務であるプロダクト開発や事業戦略に一層集中できます。弊社でも大企業の新規事業支援の実績を多数有しており、最適なプランをご提案できます。新規事業成功へのパートナーとして、まずはお気軽にお問い合わせください。本記事の内容がお役に立ち、皆様の新規事業が成功裏に軌道に乗る一助となれば幸いです。
営業代行ならプロセルトラクションにご相談ください
プロセルトラクションでは、皆様のご要望に合わせた営業代行サービスを提供しています。リクルートなどの大企業からスタートアップまでサポート経験豊富な営業のプロがあなたの会社をサポートいたします。